��Q�P�b�@�S���t�ꗘ�p�ł̊�

�@�݂Ȃ���́A�S���t�ꗘ�p�łƂ������̂�����̂������m�ł����H
�@
�@�S���t�ꗘ�p�łƂ́A���̖��̒ʂ�A�S���t��i�S���t���K��������j��
���p����ۂ��ېł����ŋ��̂��Ƃł��B
�@����͓��{�̒n���Ŗ@�i���a25�N7��31���@����226���j�Ɋ�Â���
�s���{�����ۂ����ŋ��ł���A�[�t���ꂽ�ŋ��̂����A70���͂��̃S���t�ꏊ�݂̎s������
��t����邱�ƂɂȂ������܂��B
�@�S���t�ꗘ�p�ł̉ېł̗��R�́A���2����܂��B
�@�@�@�S���t��̗��p���͑��̃X�|�[�c�ɔ�ׂĂ��������̂ƂȂ��Ă���A
�u�S���t��𗘗p���邨�q����͒S�ŗ́i�Ł@����[�߂�\�́j�������v�ƍl�����邽�߁B
�@�A�@�S���t��ɌW��J�����A���H�����Ȃǂ̍s���T�[�r�X�͐��S���t��̗��p�҂�
�A�����邱�Ƃ���A���p�҂ɂ����̔�p�S�����邽�߁B
�@�S���t�ꗘ�p�ł̐Ŋz�́A�S���t��ɂ���ĈقȂ�A�S���t��̋K�͂���ɉ�����
��߂��Ă��܂����A��ʓI�ɁA�P�l�P��800�`1,200�~�̊ԂŒ�߂��Ă��܂��B
�i1,200�~������ł��j�B
�@�������A�ȉ��ɊY������ꍇ�̓S���t�ꗘ�p�ł���ېłƂȂ�܂����A���̏ꍇ�ł��A
�S���t��ɔ����t���́u�S���t�ꗘ�p�Ŕ�ېŊY���͏o���v���o���A
�u�^�]�Ƌ��E��Q���蒠�Ȃǁv�̏ؖ������K�v�ƂȂ�܂��B
�E�N�18�Ζ����̎ҁA�܂���70�Έȏ�̎҂��S���t��𗘗p����ꍇ
�E��Q�҂̕����S���t��𗘗p����ꍇ
�E�w�Z�̋��犈���Ƃ��ăS���t��𗘗p����ꍇ
�E�����̈���ɎQ������S���t�I��
�@�S���t�ꗘ�p�ł́A�S���t��̌o�c�ғ������ʒ����`���҂ƂȂ�A
���p�҂���S���t������p�����ƈꏏ�ɃS���t�ꗘ�p�ł����A
�S���t�ꏊ�݂̊e�s���{���\���A�[�t���邱���ƂȂ�܂��i�S���t�ꗘ�p�ł�
�s���{���łł��̂ŁA�e�s���{���ɂ���Đ\���A�[�t�������قȂ�܂��j�B
�@�S���t����悭���p�������́A�n��ɍv�����Ă���Ƃ������Ƃ��ӎ����Ă݂�ƁA
�S���t���܂��܂��y�����Ȃ邩������܂���B
��Q�Q�b�@�����ł̊�

�����̔�������Ă���鉷��B
����ȉ���𗘗p����ہA�����łƂ����ŋ�������Ă��邱�Ƃ�
�m���Ă��܂������H
�@
�@�����łƂ́A �z��ɂ���������s�ׂɑ��ĉېł����
�s������(�n����)�̂��Ƃł��B
�n���Ŗ@�ɒ�߂��Ă���ړI�łɂ�����܂��B
�h���A���A����킸�A����(�z��)�𗘗p����Ήېł���܂��B
�ŋߑ������Ă���X�[�p�[�K��(��ʌ��O����ȊO�̌��O����)�Ȃǂ�
�ېőΏۂł���ꍇ�������悤�ł��B
�z��Ƃ́A�����Ƃ��ĉ���𗘗p���闁��������܂��B
�@�����z���݂���s�����ł́A�����{�݂Ɠ��Y�s�����̍s���T�[�r�X�Ƃ̊Ԃ�
���ڂȊ֘A��������܂��B�����ŁA���̗��p�҂ɉ����̕��S�������A���̎������A
���q���{�݁A�z�̕ی�Ǘ��{�y�я��h�{�݂��̑����h�����ɕK�v��
�{�݂̐����ɗv�����p�A�Ȃ�тɊό��̐U���ɗv�����p�ɏ[�Ă邱�ƂƂ���Ă���̂ł��B
�@�����ł́A�����{�݂��A�����q1�l1���ɂ��A�W����150�~���x���s�����ɑ����Ē������A
�����̂ɔ[�߂܂��B�������A�������ɓ����ł��܂܂�Ă���ꍇ���قƂ�ǂł��B
�����{�݂͊e�s���������Œ�߂�����܂łɁA�\�������o���A�[�t���邱�ƂƂȂ��Ă��܂��B
�@�ʏ�A���{�ɂ�����[�ŋ`���҂ɂ�����[�Ŋz�̌v�Z�ɂ����ẮA
100�~�������̂ĂƂ���[�u������Ă��܂����A�����ł�100�~�����ł����Ă�
���̒[�����̂ĂȂ��[�u���Ƃ��Ă��܂��B�i���j
�i���j���Œʑ��@��119���i���ł̊m����z�̒[���v�Z���j��1���̋K��
�@�@�@�n���Ŗ@��20����4��2�i�ېŕW���z�A�Ŋz���̒[���v�Z�j��3���{���̋K��
�@�@�@���@����������������ђn���Ŗ@�{�s�ߑ�6����17
�@�@�i�ېŕW���z�y�ѐŊz�̒[���v�Z�̓���j��2���̋K��ɂ��B
�������A�ȉ��̍��ڂɊY������ꍇ�͖Ə�����܂��B
�@�i�P�j�N��P�Q�Ζ����̎�
�@�i�Q�j�������ꖔ�͈�ʌ��O����ɓ��������
�@�i�R�j�w�Z����@�i���a�Q�Q�N�@����Q�U���j��P���ɋK�肷��w�Z�̎����A���k�A�w��
�@�@�@�@�y�ш����҂ŋ����̌��n����s����s���ɎQ�����A����������́B
�@����D���ɂ͐g�߂ȓ����łł����A����ɓ����Ă���Ƃ��ɂ́A
�ŋ��̂��Ƃ͖Y��Ė����ꂽ���Ƃ����̂��{����������܂���ˁB
��Q�R�b�@�@�����̏��n�̊�
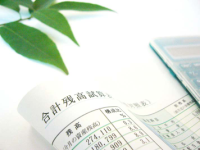
�@���̔����ŗ��v���o���ꍇ�A�m��\���ł͂ǂ̂悤��
������̂ł��傤���B
����͊����̏��n�ɂ��ďЉ�܂��B
�@�������̗L���،��̏��n�ɂ�鏊���ɂ��ẮA���̏����Ƌ敪
���Đŋ����v�Z���镪���ېł̕��@�ɂ��ېł���܂��B�Ȃ��A
�������̏��n�����ɂ́A��ꊔ�����̏��n�A���ꊔ�����̏��n������A���ꂼ��A�قȂ�ŗ����K�p����܂��B
�P�D��ꊔ���̏��n
�@��ꊔ���Ƃ́A�،�������ɏ�ꂵ�Ă��銔���A�X�������o�^�����Ƃ��ēo�^����Ă��銔��
�Ȃǂ̂��Ƃ������܂��B
�@��ꊔ�����̏��n�v�ېłɂ́A����������x�Ƃ������̂��݂����Ă���A����͏،���Г�������������Ŕ��p������ꊔ�����ɂ��āA�P�N�Ԃ̔������v�𓊎��Ƃɑ����Čv�Z���鐧�x
�ł��B�،���Г����쐬����u��������N�Ԏ�����v��p���ĊȈՂɊm��\�������邱�Ƃ�
�ł��܂��B
�@�܂��A�u��������v��I�����܂��ƁA�m��\���͕s�v�ł����A�e�����Ԃ̏��n������
���v�ʎZ����ꍇ�A�z�������Ƒ��v�ʎZ����ꍇ�y�я�ꊔ�����ɌW����n�������J�z�T������
����̓K�p����ꍇ�Ɋm��\��������K�v������܂��B
���j�����̎葱�������Ă��Ȃ�����A��ʌ����̕��́A�K���m��\�����K�v�ɂȂ�܂��B
���������̏��n�����i���n�v�j�̐Ŋz�Z�o���@��
�������z�|�i�擾��{�ϑ��萔�����j���������̏��n�������z
�������̏��n�������z�~�ŗ����Ŋz
���j�ŗ��@����15�N1��1���`����25�N12��31���@�@10���i�����Ł@7���A�Z����3���j
�@�@�@�@�@����26�N�ȍ~�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@20���i������ 15���A�Z����5���j
���j�m��\���������ꍇ�A���v�������z�Ɋ܂܂�܂��B�������N�ی��̎Z���}�{�̔���A
�@�@�e�틋�t�i������j���ɉe�����o�邱�Ƃ�����܂��̂ŁA�\���̍ۂɂ͒��ӂ��Ă��������B
�Q�D���ꊔ���̏��n
�@���ꊔ���Ƃ́A�،�������ɏ�ꂵ�Ă��銔���A�X�������o�^�����Ƃ��ēo�^����Ă��銔�����ȊO�̂��Ƃ������A�����J���E���ꊔ�E����J���Ƃ������܂��B
�@���ꊔ�������n�����ꍇ�A���n���鑊�肪���̊����̔��s�@�l�ł��邩�A
�����łȂ����ɂ���ĉېŕ��@�y�ѕ��S���ׂ��Ŋz���傫���قȂ邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�����Ƃ��āA���ꊔ�������n�����ꍇ�ɂ́A�������n�v�ɑ���20%(������15%�A
�m��\�����K�v���s�v���A�m��\�������邱�Ƃɂ���đ������Ȃ������A
�������m����g�ɂ��āA�\���R�ꂪ�Ȃ��悤�ɂ������ł��ˁB
��Q�S�b�@�����̔z���̊�

�@�O���̏��n�ɂ��Ă��b���܂����̂ŁA
����͔z�������ɂ��Č��Ă����܂��傤�B
�@�z�������Ƃ́A�����o���҂��@�l�����z���Ⓤ���M��
�i���Ѝ����M���y�ь�����Ѝ��^�p�����M���ȊO�̂��́j�y��
�����v�،����s�M���̎��v�̕��z�ȂǂɌW�鏊���������܂��B
�z�������̋��z�́A���̂悤�Ɍv�Z���܂��B
�z�������̋��z��
�@�@�@�@�������z(���������O�̋��z)�|�����Ȃǂ��擾���邽�߂̎ؓ����̗��q
�i���j�������z���獷���������Ƃ��ł���ؓ����̗��q�́A�����Ȃǔz���������ׂ����{��
���̔N�ɂ�����ۗL���ԂɑΉ����镔���Ɍ����܂��B�Ȃ��A���n���������ɌW����̂�m��\�������Ȃ����Ƃ�I�������z���ɌW����̂Ȃǂɂ��ẮA�������z���獷���������Ƃ��ł���
�ؓ����̗��q�ɂ͓�����܂���B
�@�z�������́A�z�����̎x���̍ۂɏ����œ�����������܂��B�������ꂽ�����ł́A
�P�D��ꊔ���̔z��
�@����21�N1��1�����畽��25�N12��31���܂ł̊ԂɎx������ׂ���ꊔ�����̔z������
���ẮA7%(���ɒn����3%)�̌y���ŗ��ɂ�茹������܂��B�Ȃ��A����26�N1��1���Ȍ�Ɏx��������ׂ���ꊔ�����̔z�����ɂ��Ă�15%(���ɒn����5%)�̐ŗ��ɂ�茹������܂��B
(��) ���s�ϊ����̑�������5%�ȏ�i����23�N10��1���Ȍ�Ɏx������ׂ��z�����ɂ��Ă�3���ȏ�j�ɑ������鐔���͋��z�̊�������L����l�i�ȉ��u������哙�v�Ƃ����܂��B�j��
�x�������ꊔ�����̔z�����ɂ��ẮA���̌y���ŗ��K�p�̑ΏۂƂȂ�܂���̂ŁA
20��(�n���łȂ�)�̐ŗ��ɂ�茹������܂��B
�Q�D���ꊔ���̔z��
�@���ꊔ���̊���z�����ɂ��ẮA�@�l����A�l����Ƃ�������20%�݂̂�����
����܂��B�����łɂ��ẮA�����A�m��\�����K�v�ł����A1����������1��5���~
(�N1��10���~)�ȉ��̏��z�z���́A�m��\����v���Ȃ����ƂƂ���Ă��܂��B�������A�Z���łł͔��ꊔ���̔z���ɂ��āA�m��\���s�v���x�͂���܂���̂ŁA�Z���ł̐\�����K�v�ł��B
�R�D�z�������̉ېŕ��@
�@�z�������́A�����Ƃ��Ċm��\���̑ΏۂƂ���܂����A�m��\���s�v���x��I�����邱�Ƃ�
�ł��܂��B�܂��A����21�N1��1���Ȍ�Ɏx������ׂ���ꊔ�����̔z�������ɂ��ẮA
�����ېłɂ�炸�A�\�������ېł�I�����邱�Ƃ��ł��܂��B�i�\�������ېł̑I���́A�m��\��������ꊔ�����̔z�������̑S�z�ɂ��Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B�j
�i�P�j�����ې�
�@�z�������̉ېłɂ́A�����ېłƂ������̂�����܂��B�����ېłƂ́A�e�폊�����z�����v���ď����Ŋz���v�Z����Ƃ������̂ł��B�����ېł̑ΏۂƂ����z�������ɂ��ẮA���̂��̂�
�����z���T���̓K�p���邱�Ƃ��ł��܂��B
�i�Q�j�m��\���s�v���x
�@�z�������̂����A���̂��̂ɂ��Ă͔[�Ŏ҂̔��f�ɂ��m��\�������Ȃ��Ă��悢���Ƃ�
����Ă��܂��B������u�m��\���s�v���x�v�Ƃ����܂��B�m��\���s�v���x�̑ΏۂƂȂ�z�����́A��Ɏ��̂Ƃ���ƂȂ��Ă��܂����A���̐��x��K�p���邩�ǂ����́A1��Ɏx������ׂ��z�����̊z���ƂɑI�����邱�Ƃ��ł��܂��i�����I���������̔z�����ɂ��ẮA�������ƂɑI�����邱�Ƃ��ł��܂��i����22�N�Ȍ�j�j�B�Ȃ��A�m��\���s�v���x��I�������z�������ɌW�錹���Ŋz�́A���̔N���̏����Ŋz���獷���������Ƃ͂ł��܂���B
�@o��ꊔ�����̔z�����̏ꍇ�i������哙����ꍇ�������܂��B�j�@
�@�x������ׂ��z�����̋��z�ɂ�����炸�A�m��\����v���܂���B
o��ꊔ�����ȊO�̔z�����̏ꍇ
�@���Ɏx������ׂ��z�����̋��z���A���ɂ��v�Z�������z�ȉ��ł���ꍇ�ɂ́A�m��\���@��v���܂���B
�@�@�@�@�@�@ 10���~�@�~�@�z���v�Z���Ԃ̌����i���j�@���@12
�i���j��L�̏�ꊔ�����̔z�����ɌW�錹���ŗ��ɑ���y���ŗ��̓���[�u�y�ъm��\��
�s�v���x�ɂ́A����،������M���i���Ѝ����M���������܂��B�j�y�ѓ��蓊���@�l�̓�������
�z�������܂܂�܂��B
�ɂ��ẮA15��(���ɒn����5��)�̐ŗ��ɂ�錹�������Ŕ[�ł��������錹���ېł�
�ΏۂƂ���Ă��܂��B
�����̏��n�A�z���ɂ��Đ������������A���������������v��
�\���R��ɂ���Ė��ʂɂ��Ȃ��悤�ɒ��ӂ������ł��ˁB
��Q�T�b�@�Z��[���T���̊�

�@���N���m��\���̃V�[�Y��������Ă��܂����B
�Ƃ����l���\��������Ɛŋ����߂���������Ȃ����肷��̂ŁA
�Y�ꂸ�Ɏ葱�����������̂ł��B
�\���̕��@�⒍�ӓ_���m�F���Ă����܂��傤�B
o�����̗��N�ɐ\�����K�v�ȏZ��[���T��
�@���^����ŋ����V���������T�����[�}���ɂƂ��āA�m��\���͂Ȃ��݂̔������x
��������܂���B�������Ƃ����l�ɂƂ��ẮA�[�߂��ŋ����߂��Ă�����A�ŋ��������Ȃ�
���Ⴊ��ꂽ�肷��厖�Ȏ葱���ł��B������͐ŋ��ɂ��Ă��܂�ӎ����Ȃ��l�ł��A
�\�����邱�ƂŎ������ŋ��������略���Ă��邩���m�F����悢�@��ɂ��Ȃ�ł��傤�B
�@ �Z��֘A�̐Ő��Ŋm��\�����K�v�Ȃ��̂Ƃ����A��\�I�Ȃ��̂͏Z��[���T���i�������̂́u�Z��ؓ��������ʍT���v�j�ł��B�N���̏Z��[���c���ɉ������z�������Ԃɂ킽���ď����ł���T������邱�̐��x�́A�����������N�Ɋm��\�����邱�ƂœK�p�����܂��B
�Z��[���T���̓K�p���邽�߂ɂ́A�ȉ��̂悤�Ȃ������̏��������K�v������܂��B
o�Z��[���T�����邽�߂̎�ȏ���
�i1�j�Z��擾��6�����ȓ��ɓ������A�����������Z���Ă��邱��
�i2�j���ʐρi�o�L�ʐρj��50m?�ȏ�ł��邱��
�i3�j���ʐς�2����1�ȏオ�A��玩�Ȃ̋��Z�̗p�ɋ��������̂ł��邱��
�i4�j�T������N�̍��v�������z��3,000���~�ȉ��ł��邱��
�i5�j���Ԃ̋��Z�@�ւ�t���b�g35�Ȃǂ̏Z��[�����𗘗p���Ă��邱��
�i6�j�Z��[�����̕ԍϊ��Ԃ�10�N�ȏ�ł��邱��
o�Z��[���T���\���ɕK�v�ȏ���
�@�\���̍ۂɂ͐\�����ƈꏏ�ɁA�ȉ��̏��ނ�Y�t����K�v������܂��B
�o�L�����ؖ����i�o�L��j�Ȃǂ͈����n���̍ۂɎ�������̂��R�s�[����Α���܂����A
���߂Ď擾���悤�Ǝv���Ɠo�L���i�@���ǁj�܂ōs���Ȃ���Ȃ炸�A�萔�����K�v�ł��B
�i1�j�i���葝���z���j�Z��ؓ��������ʍT���z�̌v�Z����
�i2�j�Z���[�̎ʂ�
�i3�j�Ɖ��̓o�L�����ؖ����A�����_�̎ʂ��┄���_�̎ʂ��ȂǂʼnƉ�
�@�@�̎擾�N�����E���ʐρE�擾���z�𖾂炩�ɂ��鏑��
�i4�j�Z��[���̔N���c�����ؖ����i2�����ȏ�̋��Z�@�ւ����t����
�@�@����ꍇ�́A���̂��ׂĂ̏ؖ����j
�i5�j�~�n���̃��[���ɂ��čT������ꍇ�́A�o�L�����ؖ����┄���_��
�@�@���̎ʂ��ȂǂŁA���̕~�n���̎擾���z�E�擾�N�����Ȃǂ𖾂炩�ɂ���
�@�@����
�i6�j���^�����҂̏ꍇ�͌����[�i���{�j
�@�m��\���̊��Ԃ͗�N2��16���`3��15���̊Ԃł����A�Z��[���T���̂悤�ɂ�������[�߂��ŋ����ҕt�����ҕt�\���̏ꍇ��2��15���ȑO�ł��t���Ă���܂��B
�\�������̊ԍۂɂȂ��čQ�ĂȂ��悤�A���߂ɏ������Ă����A�\���R��̂Ȃ��悤�ɂ��������̂ł��B
��Q�U�b�@�n�k�ی����T���̊�

�@�����{��k�Ђɂ��A�n�k��⏞�ł���ی���
���ڂ��Ă���l�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�Еی�����ی��ɉ�������Ă�����͑�����
�v���܂����A�n�k�ی��̉����҂͂܂����Ȃ�
�ł��傤�B
����A�����{��k�Ђ̂悤����n�k��
���N���邩�킩��܂���B
�����ŁA�n�k�ی����T���ɂ��ĉ�����܂��B
�@�܂��A�n�k�ی��Ƃ́A�u���̎��Y��ΏۂƂ���_��ŁA�n�k���ɂ�����Q�ɂ�萶���������̊z���Ă�₷��ی����܂��͋��ϋ����x�������_��v�Ƃ���Ă��܂��B
�܂�A�n�k�ɂ���Č�����ƍ��Ȃǂ���������Q���J�o�[���邽�߂̕ی������łȂ��A
���̋��ς��ΏۂƂȂ��Ă��܂��B�܂��A�Еی���Ћ��ςɕt�т��ĉ�������
�n�k�ی��Ȃǂ��Ώۂ�������A�Ƃ���Ă��܂����A���Ƃ��ƒʏ�̒n�k�ی���
�Еی��ȂǂɃZ�b�g���Ȃ��Ɖ����ł��Ȃ��̂������͖��Ȃ��ł��傤�B
�@�ł́A�n�k�ی����T����\������ƁA�ǂꂾ���ŋ��������Ȃ�̂ł��傤���B
�n�k�ی����T���́A�������玟�̂悤�ȋ��z�������������Ƃ��ł��܂��B
�n�k�ی��������T������Ȃ�A�x�������ی����̑S�z�i�ی�����50,000�~���Ȃ��50,000�~�j
����������T�����邱�Ƃ��ł��܂��B�Z���ł̌v�Z�ł́A���̔����̊z�������T���ł��܂��B
�@�C���������̂́A�n�k�ی��Ƃ͕ʂɋ��������Q�ی��_��������Ă���l�ł��B
����18�N���܂łɌ_�����́B����19�N1��1���ȍ~�ɂ��̑��Q�ی��_�̕ύX��
���Ă��Ȃ����̂ɂȂ�܂��B�������A�ꏏ�ɍT������Ȃ�A�n�k�ی����T���ƍ��v��
50,000�~������ƂȂ�܂��B
�@�ł́A���ۂɈ����Ȃ�ŋ��z���v�Z���Ă݂܂��傤�B
���Ƃ��A�n�k�ی��̕ی�����N30,000�~�x�������Ȃ�A�����ł̌v�Z�ł͏�������30,000�~�A�Z���ł̌v�Z�ł͏�������15,000�~�T�����邱�Ƃ��ł��܂��B�����ł̐ŗ���10���̐l�ł���Ώ����ł�3,000�~�A�܂��Z���ł̐ŗ��͈ꗥ10���Ȃ̂�1,500�~�A���v4,500�~���ŋ������Ȃ��Ă��ތv�Z�ƂȂ�܂��B
�@���̂悤�ɃL�`���Ɛ\������ΐŋ������Ȃ����邱�Ƃ��ł��܂��B
�u�ʓ|�������v�ƌ��킸�ɂǂ�ǂ�\�����܂��傤�B�܂��A���ɂ͒n�k�ی��ɉ������悤��
�����Ă���l������ł��傤�B���̍T��������ΐŋ��������Ȃ镪�A�����̕ی�����
���Ȃ��Ă��ނ킯�ł��B�Еی��ɉ������Ă��邾���ł́A�n�k�ɂ��Ђ�|��ɑ���
�⏞�͂قƂ�ǂ���܂���B
������@��ɁA�n�k�ی��ւ̉������������Ă݂�̂�������������܂���ˁB
��Q�V�b�@�ł̊�
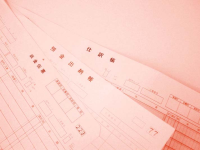
�����͈ł�[�߂邽�߂̏ؕ[�ŁA�����ڂ͂ƂĂ�
�؎�Ɏ��Ă��܂����A���̈Ӗ��͂܂������قȂ�܂��B
����́A�ł̈Ӗ��E�Ӌ`�ɂ��Ă��b���܂��B
�y�łƂ́z
�@�o�ϓI����ȂǂɊ֘A���č쐬����镶���ɉېł����
�ŋ��̂��Ƃł��B
�ł̔[�ŋ`���҂́A���̉ېŕ����ɑ��A�Ŗ@�ɒ�߂�ېŕW����
�ŗ�����ɔ[�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B
�@�܂�łƂ́A�_�E��揑�Ȃǂ�"�ؖ�"�̂��߂ɉېł����ŋ��ŁA
�_�̓��e��_����z�A�����z�Ȃǂɂ���ĈŊz����߂��Ă��܂��B
�@���̈ł́A"���K������悤�Ȍ_��͐ŋ����ۂ���ɒl����"�Ƃ����l��������
�ېł����ŋ��ł���ƍl�����܂��B
�łS����͉̂ېŕ����̍쐬�҂ł��B���������̏ꍇ�̕�����
"�_��"�ɉېł������̂ł��邽�߁A�Q�l�ȏ�̐l��������肠���Ă��邱�Ƃ�
�ʏ�ł��B
�@�܂�A���̑o���ɔ[�ŋ`��������܂��B�ʏ�A�̎����͂�������������A���_�Ȃǂ͂��������A���K�ؗp�_�Ȃǂł͂������������łS����悤�ȌX����
����܂��B
��\��Y�ꂽ�ꍇ�͒E�ł������ƂɂȂ�A���̈Ŋz�{�Q�{�̉ߑӐł�������܂��B
�����Y��Ă��z�ʑ����̉ߑӐł�������܂��B
�t�Ɉ�\��Ȃ��Ă����������Ɍ���ē\���Ă��܂����ꍇ�A
���邢�͌��߂�ꂽ���z�ȏ�̈�\���Ă��܂����ꍇ�́A
�\�����邱�ƂŁA�ŋ���ԋ����Ă��炤���Ƃ��\�ł��B
�ł́A�_�̎����ɂ��Ă��b���܂��B
�y�_�̎����z
�@�_�Ɉ�\��Ƃ������Ƃ́A���ɏ펯�ł��B�����Ƃ��Č_�ɂ�
�Ŋz�ꗗ�\�ɋL�ڂ��ꂽ�Ƃ���̈�\��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl����
�ԈႢ�͂Ȃ��ł��傤�B
�Ŋz�́A�����_��s���Y�����_�ȂǂɋL�ڂ���Ă�����z��
�����ĉېł���܂��B
�@�����Œ��ӂ������̂́A����ł̉ېŎ��Ǝ҂��쐬���錚�����̔����_�E
�^���_�E�����_�ɁA�_����z�Ə���ŋy�ђn������ł�
��̓I�ȋ��z���敪���ċL�ڂ���Ă���ꍇ�ł��B
���̏ꍇ�A����œ������z�����������z���L�ڋ��z�ƍl�����܂��̂ŁA
�ł�[�߂����Ȃ��悤�ɋC�����Ă��������B
�@�Ⴆ�A�����_�ɐ������z�P�疜�~�ƁA����ɑ������ŋy��
�n������ő����z50���~�Ƃ��敪���ċL�ڂ���Ă���Ƃ��́A���̐����_�̋L�ڋ��z��
�P�疜�~�ƂȂ�A�Ŋz�͂P���~�ƂȂ�̂ł��B
�y�_���Q���ȏ������ꍇ�́H�z
�@�P�̌_��ɂ��āA�_�����ʂ��쐬����ꍇ������܂����A
���̏ꍇ�ɂ́A���̑S���Ɏ������͂�Ȃ���Ȃ�܂���B
�܂��A�u�ʁv�A�u���{�v�A�u���{�v�Ȃǂƕ\�������_�ł����Ă��A
������̏������͉���̂�����̂�A�_���҂����{�Ƒ���Ȃ����Ƃ�
�ؖ��������̂́A���{�Ɠ����悤�Ɏ������͂�Ȃ���Ȃ�܂���B
�P�ɃR�s�[������Ă������悤�Ȃ��̂ɂ́A������\��K�v�͂���܂���B
���Z���߂Â��N�x���B���̎������A�o������͎��������Ȃ蔭�s����܂��ˁB
�łɂ��Đ������������A�ԈႦ�Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B
��Q�W�b�@���̊�

�@�ꓙ�P���~�I���̂悤�ɏ����ɂƂ��Ă͂܂��ɖ��̕��ł����A
���������i�N���W�����{�Etoto�E�i���o�[�Y�E���g6�Ȃǁj
�ɓ��I�����ꍇ�A�ŋ��i�����ŁE�Z���Łj�͂�����̂ł��傤���H
�@�l�������̓��I���͔�ېłƂȂ��Ă��܂��̂ŁA
�Ⴆ���łP���~�����������ꍇ�ł��A�ŋ��͈������܂���
�̂Ŋm��\�����K�v����܂���B
�@�Ȃ����̓��I���͔�ېłȂ̂��H�Ƃ����ƁA�Ⴆ�W�����{���̏ꍇ��40���i1��
300�~�̃W�����{���̖�120�~���j�͎��v���Ƃ��Ĕ������̊e�����̂̎��v�ƂȂ��Ă��܂�
�̂ŁA�������͕��̓�����O��ɊW�Ȃ��A�����w���������_�ł��łɐŋ����Ă���
���������ƂȂ̂ŁA���I�����炳��ɐŋ�������邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł��B
�� ���Őŋ����������Ă��܂��ꍇ ��
�@�l�����̓��I�������ꍇ�̐ŋ��͂�����܂��A���������I�����Ƒ��A�F�l�A
�m�l�Ȃǂ����z���Ă��܂��ƁA���R�u���^�Łi1�l�ɑ��ĔN��110���~�ȉ��̑��^�ł����
���^�ł͂�����܂���j�v�̑ΏۂƂȂ�܂����A���ɕ����O���[�v�ōw�����Ă����ꍇ�ł�
���I����1�l�Ŏ���Č���O���[�v�̃����o�[�ɕ��z�����ꍇ�����l�ɑ��^�ł̑Ώۂ�
�Ȃ�܂��̂ŁA���I���z�������ꍇ���K����s�Ŏ��ۂɁA���z�������l�S���̖��`��
���悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B�i���l�̏����E�����ϔC�K�v�ł��j
�@�Ⴆ��2�l�ŕ����w�����i�O���[�v�����j1���~�̕������I�����ꍇ�A1�l�œ��I��1���~�����A��ɂ��������5�疜�~�z����Ƃ�����ȉ��̂悤�ȑ��^�ł�������܂��B
�@�@�u�i���^�z-��b�T���z110���~�j�~�ŗ�-�T���z�����^�Ŋz�v
�@�@�u�i5,000���~-110���~�j�~50���i���^�ł̍ō��ŗ��j-225���~��2,220���~�v
�@5,000���~�^����ƁA�Ȃ��2,220���~�����^�ł��������Ă��܂��̂ł��I
�@���^�ł̐ŗ��͍����̂ŁA���������ō��z���I����ɕ��z����Ƃ������ꍇ�́A�K��
���z�������l�S���̖��`�Ŏ��悤�ɂ��Ȃ���A���Ȃ荂�z�ȑ��^�ł�[�t���邱�Ƃ�
�Ȃ�܂��̂����ӂ��Ȃ��Ƃ����܂���ˁB
��Q�X�b�@�}�C�z�[���̊�

�@�l���ň�ԍ����Ȕ������Ƃ�����u �}�C�z�[�� �v�B
�������}�C�z�[�����w�����邽�߂ɂ͓y�n�E�����Ȃǂ����łȂ��A�l�X�Ȕ�p���������Ă��܂��B
�@���Ƀ}�C�z�[���ɂ͈ێ����邽�߂ɂ��ŋ����������Ă��܂��̂ŁA���O�ɂ������l�����Ȃ���Ȃ�܂���B
�� �}�C�z�[���w�����ɂ������Ă���ŋ� ��
�@�@�E�_�ɂ�����ŋ� �ˁu�Łv
�@�@�E�}�C�z�[����o�L����Ƃ��ɂ�����ŋ� �ˁu�o�^�Ƌ��Łv
�@�@�@�@�� �o�^�Ƌ��ł̃}�C�z�[������i�y���ŗ��j�����܂��B
�@�@�E�o�L��ɂ�����ŋ� �ˁu�s���Y�擾�Łv
�@�@�E�w�����錚���ɂ�����ŋ� �ˁu����Łv
�@�@�@�@�� �y�n�͔�ېłł����A����萔���͓y�n�ɂ�����ł�������܂��B
�� �}�C�z�[�����ێ����邽�߂ɂ������Ă���ŋ� ��
�@�@�E�ێ����邽�߂ɂ�����ŋ� �ˁu�Œ莑�Y�ŁE�s�s�v��Łv
�� �s���Y�i�}�C�z�[���j�����n�����ꍇ�ɂ������Ă���ŋ� ��
�@�@�E�y�n�A�����A�ؒn���Ȃǂ����n�����ꍇ�ɂ�����ŋ� �ˁu���n�����v
�@�@�@�@�� �@���̗v�������A���n�v(���n����)����ō�3,000���~�̍T����
�@�@�@�@�@���܂��B
�@�@�@�@�@�@�܂����L���`�̏ꍇ�A�e�����v���������ꂼ��ɍT�����邱�Ƃ�
�@�@�@�@�@�ł���̂ŁA�v�w�̋��L���`�ł���Ίe3,000���~�~2�����̍ō�6,000���~��
�@�@�@�@�@�T��������̂ł��B
�@�@�@�@�@�@������̍T���������n�������Ȃ��ŋ����x����Ȃ��ėǂ��Ȃ���
�@�@�@�@�@�ꍇ�ł��A�m��\���͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂Œ��ӂ��܂��傤�B
�@�ȏ�̂悤�Ƀ}�C�z�[�����w�����鎞��ێ����鎞�͂������A���n�i���p�j����ۂɂ��ŋ����������Ă���̂ł��B
�@�}�C�z�[���p���Ĕ��p�����o���ꍇ�́A���̏��������Ίm��\�����đ��v�ʎZ���邱�Ƃɂ���āA���̏������甄�p�����ۂ̑����������������Ƃ��ł���ꍇ������܂��B
�@�܂��A�}�C�z�[����������ꍇ�́u�}�C�z�[����3,000���~���ʍT���v�ɑウ�āA���̏��������u�}�C�z�[���̔����ւ�����v�Ƃ��āA���̏��n�܂ŏ��n�������ېł���Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��ł���ꍇ������܂��B
��R�O�b�@�G�R�J�[���ł̊�

�@�ȑO�A�����ԐŁE�y�����ԐŁE�����Ԏ擾�ŁE�����ԏd�ʐłƂ��������Ԃ��ւ��łɂ��Ă��b���܂������A����͂��̐ł������Ȃ�Ƃ������b���ł��B�F������b�l�ȂǂŁu�G�R�J�[���Łv�Ƃ������t�������Ƃ�����̂ł��Ȃ��ł��傤���B
�@���́u�G�R�J�[���Łv�Ƃ́A�r�o�K�X��R��\�ȂǁA�����\�ɗD�ꂽ�����Ԃ��w������Ƃ��ɁA���̏��������Ă���Ύ����ԏd�ʐŁE�����Ԏ擾�ł����ł����Ƃ������́B�V�ԍw���̏ꍇ�́A�G�R�J�[�⏕���ƕ��p����
�邱�Ƃ��ł���̂ŁA������p��}�����܂��B�܂��A���ÎԂ��w������ꍇ�ł��A������
�������Ă�����G�R�J�[���ł��邱�Ƃ��ł���A�Ƃ����̂��|�C���g�ł��B
�y�V�ԍw���̏ꍇ�z
�����ŗ�100���i�ƐŁj�̑Ώێ�����
�@�E�d�C�����ԁA�R���d�r�ԁA�v���O�C���n�C�u���b�h��
�@�E�V�R�K�X�����ԁA�n�C�u���b�h�ԁA�f�B�[�[���Ԃ̒��ŔR��A
�@�@�r�o�K�X�̊�l���N���A���Ă������
�@
�����ŗ�50���`75���̑Ώێ�����
�@�E�V�R�K�X�����ԁA�f�B�[�[���ԁA�K�\�����Ԃ̒��ŔR��A
�@�@�r�o�K�X�̊�l���N���A���Ă������
�y���ÎԂ̏ꍇ�z
�@�G�R�J�[���ł́A�V�ԍw���������łȂ��A���ÎԂ̍w�����ɂ��K�p����܂��B
�ΏۂƂȂ�G�R�J�[�́A��{�I�ɂ͐V�Ԃ̃G�R�J�[���őΏێԂƓ����ł����A
��l�⌸�ŗ����Ⴂ�܂��B
�@�����Ԏ擾�ł͐V�ԂƓ����������ԍw�����A�����ԏd�ʐł͎Ԍ����Ɍ��ő[�u��
�邱�Ƃ��ł��܂��B
�@���݁A�e�����ԃ��[�J�[�Ŋ����\�ɗD�ꂽ�����Ԃ��J������Ă��܂��B
�V���������鎩���Ԃ̂��̂قƂ�ǂ��R���r�o�K�X�ɔz���������őΏێԂł����
�����Ă��ߌ��ł͂���܂���B�����A�����Ԏ�ł��d�l�ɂ���Č��ł̑ΏۂƂȂ邩
�ǂ�����A���ŗ����ς��Ƃ����P�[�X���������߁A�w������ۂ͊e�f�B�[���[����
�m�F���K�v�ł��B
�@
�@�������̐����ɂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����̂ƂȂ��������ԁB�����������ł�m����
�������ƂŁA�ƌv�ɂ��A���ɂ��D�������邱�Ƃ��ł����ł��ˁB