��R�P�b�@���E�̐ŋ��̊�

�@���܂ŐF�X�ȍ����̐łɂ��Ă��͂Ȃ����Ă��܂������A����͂�����ƃu���C�N�B���E�̂������낢�łɂ��Ă��b���Ă݂悤�Ǝv���܂��B�݂�����͐��E�ɂ���Ȃ������낢�ł�����̂�m���Ă��܂����H
�� �|�e�g�`�b�v�X��
�@�����̔얞�h�~��ړI�ɁA�n���K���[�œ����B�X�i�b�N�َq����������ȂǁA�����ⓜ�������ɍ����H�i���ېőΏۂƂȂ�B
�� �a�ؐ�
�@�C�M���X�̃����h�����S���Ŏ{�s����Ă���ŁB�����̈�莞�ԓ��Ɍ��߂�ꂽ�G���A�ɎԂŐi������Ɖېł����B�a�����풃�ю��ƂȂ��Ă��邱�̃G���A�̍��G�����炵�A���̌�ʋ@�ւ̗��p�𑣂��ړI�œ����B
�� �����
�@�t�B�������h�������[�e���h����E�I�[�\�h�b�N�X������h�̋���o�^�҂��ΏۂƂȂ�ŁB����̎����͂���Řd���Ă���B
�� ���邨�������
�@�l����������ړI�ō��ꂽ��������ɂ͉ېł���Ƃ������́B�ԉ₨������̏e�Ȃǂ����̑ΏۂƂȂ�B���̐ł���������Ă���A�����J��E�F�X�g�o�[�W�j�A�B�̋����ƍ߂����Ȃ��̂͂��̐ł̂������H
�@�ȂǂȂǁA���ɂ����E�ɂ͒n���F���ӂ��ŋ��������ς�����܂��B�u�|�e�g�`�b�v�X��H�ׂ�̂ɐŋ����x�����Ȃ�āI�v�Ǝv����������邩������܂��A�n���K���[�ł͂��ꂾ�����̔얞�����莋����Ă���Ƃ������ƁB
�@���E�̍��X�ł͂��܂��܂Ȃ����ŁA�Ŏ��𑝂₵����A�����̐��������P�����肷�邽�߂Ɏ��s���낳��Ă���̂ł��ˁB�@
�@
�@���āA�݂Ȃ���̒m���Ă���ł͂���܂������H
��R�Q�b�@���^�ł̊�

�@�v���[���g���đ����������������y�������̂ł���ˁB�ł����܂荂�z�̃v���[���g��Ɛŋ��������邱�Ƃ��E�E�E�B����͂���ȂƂ��ɋC���������A���^�łɂ��Ă��͂Ȃ����܂��傤�B
�@���^�łƂ́A�l������Y�^���ꂽ�ꍇ�ɉېł����ŋ��ł��B���^�ō��Y���擾�����҂��[�ŋ`���҂ɂȂ�A1��1������12��31���܂ł̊��Ԓ��Ɏ����^���Y�ɂ��ĉېł���܂����A���^�łɂ́u��b�T��110���~�v������܂��̂ŁA�N��110���~�ȉ��̑��^�ł���A���^�ł͂�����܂���B
�@���^�ł̑ΏۂƂȂ����
�@�@���@�{���̍��Y�@�@�E�E�E�a�����A�����Ȃǂ̗L���،��A�y�n�A�����A�M�����ȂǁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���K�Ɋ��Z�ł�����̂��ׂāB
�@�@���@�݂Ȃ����^���Y�E�E�E�����ɂ��ی����S���Ă��Ȃ����̂����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ی����A�؋��̌�����△���ō���Ə�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������ꍇ�̖Ə��z�ȂǁA�{���̍��Y�ł͂Ȃ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����悤�Ȍo�ό��ʂ�������Y�B
�@��ېō��Y
�@�@���@�@�l����̑��^�Ŏ擾�������Y�B
�@�@���@�ʏ�A�K�v�ƔF�߂��鐶����⋳���B
�@�@���@�Љ�ʔO��A�����ƔF�߂��鍁�T�A���j���A�����Ε�A�������ȂǁB
�@�@���@�����Ȃǂō��Y���擾�����҂��A�����J�n�̔N�ɔ푊���l��������^���Y�B
�@�@�@�i�������ł̑ΏۂɂȂ�܂��B�j
�@�@���@�����ɂ����Y���^
�@�u���^�v�Ƃ́A�l�����Y����֖����ŗ^����ӎv�\�������āA��������������邱�Ɓi�����ł����ʂł��j�ł��B���^�ł̏ꍇ�A������̏��������������ǂ�����������Ȃ��ꍇ�́A���^���������Ƃ��̂ƌ��Ȃ����ꍇ�������悤�ł��B
���Ƃ��ΎԂ��ȂǍ��z�̃v���[���g����������ꍇ�A110���~����悤�Ȃ��̂Ȃ瑡�^�ł̑ΏۂɂȂ�܂��̂ŁA�v���ӁI
��R�R�b�@���������Z�ېł̊�

�@�O���1�N�Ԃɑ��^�������Y�ɂ�����łɂ��Ă��b���܂������A���^�łɂ͑��ɁA���������Z�ېłƂ������x�����邱�Ƃ������m�ł��傤���B
�@�ȒP�Ɍ����ƁA�u���ꂩ�琶�O���^�Ƃ��Ď����Y�ɑ��āA���̏��������Α������ɂ܂Ƃ߂Đ��Z���邱�Ƃ������ɁA���^�ł��y�����܂��傤�v�Ƃ������x�ŁA�����l��������Y�͗ݐς�
2,500���~�܂Ŕ�ېłƂȂ�܂��B
�@2,500���~�������Y�ɑ��Ă͈ꗥ20���̐ŗ��ƂȂ�A���ۂ̑������Ɍv�Z���鑊���ł��[�Ŋz��菭�Ȃ��ꍇ�͊ҕt���邱�Ƃ��ł��܂��B���^�ł͑����ł����ŗ��������̂ň�ʓI�ɂ͑��^�łʼnېł����������������Z�ېŐ��x��I�������ق����L���Ƃ����܂��B�܂��A�����ł̌v�Z���ɂ͑��^���ꂽ�Ƃ��̎����Ōv�Z����邱�Ƃ��|�C���g�ł��B
�@�K�p�Ώۂ͌����Ƃ���65�Έȏ�̐e����20�Έȏ�̎q���ւ̑��^�i�N��͑��^�̔N��1��1�����݂Ŕ��f�j�ƌ����Ă���A���������Z�ېŐ��x�Ɨ�N�ېŐ��x�A�ǂ���̐��x��I�����邩�͑��^�����q�������߂邱�Ƃ��ł��܂��B
�@���|�C���g
�@�@�@�E�ېʼn��i�F���^���̎����ŁA���^�Җ��Ɍv�Z�B
�@�@�@�E���ʍT���F2,500���~�i�ŏ��̑��^���瑊�����܂ł̑��^���Y���ׂĂ��Ώہj
�@�@�@�E�ŗ��F20��
�@�@�@�E�K�p�͈́F�P�x���̐��x��I���������^�҂���̑��^�́A���N�ȍ~��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�K�p���邱�ƂɂȂ�A�P��͂ł��Ȃ��B
�@���v��
�@�@�@�E65�Έȏ�̐e����20�Έȏ�̎q�ւ̑��^�ł��邱��
�@�@�@�@�i�Z��擾�������̏ꍇ�ɂ́A�e�̔N����Ȃ��j
�@�@�@�E���^�����N�̗��N2��1���`3��15���܂ł̑��^�ł̐\�����ԓ��ɁA
�@�@�@�@���^�ł̐\���ƈꏏ�Ɂu���������Z�ېőI��͏o���v�̓͏o�����邱��
�@
�@���݂ɁA���̐��x�͕��ꂲ�ƂɑI�����\�ł��̂ŁA���e����̑��^�͑��������Z�ېŐ��x�𗘗p���āA��e����̑��^�͗�N�ېŐ��x�𗘗p����Ƃ������Ƃ��ł��܂��B
�i�����������̏ꍇ�A���e����̑��^�ɂ��Ă͂������̐��x��I������Γ�x�Ɨ�N�ېłɖ߂邱�Ƃ͂ł��܂���B�j
��R�S�b�@�����ł̊�

�@�l�ԁA�����͓V�ɏ������Ƃ�������Ă��܂��B
����Ȏ��A���ƂɈ₵���l�����̂��߂ɒm���Ă��������̂������ŁB
�������̎��ɍQ�ĂȂ��悤�A����͑����łɂ��ĊȒP�ɂ��b���܂��傤�B
�@�����ł́A�e���Ȃǂ����S�������Ƃɂ����Y�����p�����ꍇ��⌾�ɂ����Y��������ꍇ�ɐ�����ŋ��ł��B�����́A�l���S���Ȃ���������n�܂�܂��B���S�����l��푊���l�ƌĂсA�����ɂ���č��Y�����p�����l�𑊑��l�ƌĂт܂��B
�E�������Y�̉ېʼn��i�@
�@�@�{���̑������Y�iex.�a�����A�y�n�A�Ɖ��A�����Ȃǁj�{
�@�@�݂Ȃ��������Y�iex.�����ی����A���S�ސE���Ȃǁj�{
�@�@�����J�n�O3�N�ȓ��̑��^���Y
�@�@�i�x�����Ă��鑡�^�Ŋz�ɂ��Ă͑����Ŋz����T���ł��܂��B�j�|
�@�@���iex.�ؓ����A�x�������A���[�ŋ��Ȃǁj
�E�@�葊���l
�@�@�@�@�葊���l�͈̔͂͌����Ƃ��Ė��@�̋K��ɂ��܂��B�����������Ŗ@�ł�
�@�@�����ł̌v�Z������ɂ������āA���@�Ƃ͕ʂɋK�肵�Ă��܂��B
�@�@�@�y�z��ҁE�q���E����E�Z��z
�E��b�T���z
�@�@�@�����łɂ͎��̊�b�T��������A�S���Ȃ����l�̍��Y����b�T���z�ȉ��̏ꍇ��
�@�@�����ł��x�����K�v�͂Ȃ��A�܂��A�\��������K�v������܂���B
�@�@�@�T�C�O�O�O���~�{�i�P�C�O�O�O���~�~�@�葊���l�̐��j
�@
�@�������Y�̉ېʼn��i�����b�T���z���������������z���u�ېň�Y�z�v�ƂȂ�A�����
�ŗ������������z�������łƂȂ�܂��B
�@
�@�����͐e���̂����Ȃ�̕s�K���Ƃ���n�܂���̂ł����A�Q���Ă���������܂���B
���̂Ƃ��ɂȂ��čQ�ĂȂ��悤�A�܂������̂��ƂʼnƑ��������߂��肵�Ȃ��悤�A
���C�Ȃ����ɑ����ő���l���Ă݂Ă͂������ł��傤���B
��R�T�b�@�����ی����T���̊�

�@�N�������̍ۂɂ悭���ɂ���A�u�����ی����T���v�B
�P�O�����炢�ɂȂ�Ɛ����ی���Ђ���u�����ی����̍T���ؖ����v�������Ă��āA�N�������̏��ނƈꏏ�ɋ��^�S���҂ɓn���܂���ˁB���̐����ی����T���̐��x������24�N���̔N�����������������Ă��邱�Ƃ������m�ł��傤���B
�@����܂ł́u��ʐ����ی����T���v�Ɓu�l�N���ی����T���v��2��ނ̐����ی����T���Ƃ���Ă��āA�e�X�̍T���̓K�p���x�z��5���~�i���v�K�p���x�z��10���~�j�ł����B
�@����24�N���Ȍ�̏����ł���u��ʐ����ی����T���v�u����Õی����T���v�u�l�N���ی����T���v��3��ނ̍T�����x�ɂȂ�A���ꂼ��̐��x�Ŏ��̇@�`�B�̊e�����ی����T���ɂ��v�Z�����T���z�̍��v�K�p���x�z��12���~�Ƃ���܂��B
�@�@����24�N1��1���Ȍ�ɒ��������ی��_�ɌW��T���i�V�_��j
�@�A����23�N12��31���ȑO�ɒ��������ی��_�ɌW��T���i���_��j
�@�B�V�_��Ƌ��_��̗����ɂ��ĕی����T���̓K�p����ꍇ�̍T��
�@���@�V�����x�����̓K�p������ꍇ�ɂ́A�V���u��ʐ����ی����T���v�A�V��
�@�u�l�N���ی����T���v���ꂼ��̍T�����x�z��4���~�ƂȂ�A���̏ꍇ�ł�
�@3���T�����v�z�́A�����ł�12���~�����x�ɂȂ�܂��B�@
�@�Ȃ��A���u��ʐ����ی����T���v�A���u�l�N���ی����T���v�̍T���z��4���~���ƂȂ�ꍇ�ɂ́A�����x�K�p�_��݂̂�\�����邱�ƂŁA���ꂼ��̍T���g���Ƃ�5���~�܂ł̍T�����\�ƂȂ�܂��B�i���̏ꍇ�ɂ����Ă�3�̍T�����v�z��12���~�����x�ł��B�j
�@
�@���_���̕����V���ɉ���Õی��ɉ������邱�ƂŁA�T���z�������A�ߐłɂȂ�܂��B�N�������̏��ނ������ŋL�����Čv�Z���Ă݂�Ƃ悭�킩��܂��̂ŁA����Ă݂�̂��ʔ������̂ł���B
��R�U�b�@�������ʏ����ł̊�

�@����25�N1��1������A�������ʏ����ł��n�݂���܂����B
�@����͓����{��k�Ђ���̕����������m�ۂ��邽�߂ɑn�݂��ꂽ���x�ŁA�l�̕��ŏ����ł�[�߂�`���̂�����́A����49�N12��31���܂ł�25�N�ԁA�����Ŋz��2.1�������ʏ����łƂ��Ĕ[�߂�Ƃ������̂ł��B
�@���@�[�ŋ`����
�@�@�@�@�l�̕��ŏ����ł�[�߂�`���̂����
�@���@�ېőΏ�
�@�@�@�@����25�N�P���P�����畽��49�N12��31���܂ł̊Ԃɐ����鏊��
�@�@�@�@�i���@���^�����҂̕��́A����25�N1��1���ȍ~�Ɏx�����鋋�^������
�@�@�@�@�@�������ʏ����ł���������邱�ƂƂȂ�܂��B�j
�@���@�������ʏ����Ŋz�̌v�Z�y�Z���z�@
�@�@�@�@�������ʏ����Ŋz��������Ŋz�~2.1��
�@���̕������ʏ����łŁA�܂��C��t���Ȃ�������Ȃ��̂͋��^���獷��������錹���ŁB
�u�����`���҂́A����25�N1���ȍ~�Ɏx�����鋋�^�ɂ��Ē������ׂ������Ŋz��2.1�������z�����ʏ����łƂ��āA�����ł̌����ƕ����Č������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ���Ă���A���^�v�Z����ۂɂ͍��܂Ŏg���Ă��������Ŋz�\�ł͂Ȃ��A�������ʏ����ł��������ꂽ�Ŋz�\�Ōv�Z���邱�ƂɂȂ�܂��̂ŁA�����`���҂̕��͗v���ӂł��B
�@�܂��A�a�������ɂ����̐ł�������܂��B����܂ŏ�����15���A�Z����5���̍��v20�����ېł���Ă��܂������A����25�N�ȍ~�͕������ʏ�����0.315���i��������15���~2.1���j�ƍ��킹���v20.315���ƂȂ�܂��B
���܂łƔ�ׂĎ��肪���Ȃ��Ȃ�̂��ƌv�ɂ͐h���Ƃ���ł��ˁB
��R�V�b�@10��ނ̏����̊�
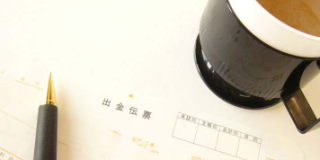
�u�����Łv�Ƃ́A���N1��1������12��31���܂ł�
1�N�Ԃɓ��������̋��z�ɂ�����ŋ��ł��B
�@���̏����̋��z�Ƃ́A���̔N�̎������z���炻�̎����邽�߂ɂ��������K�v�o��A�������͈��̍T���z�������������c��̋��z�������̂ł����A���̏����ɂ�10��ނ̋敪������܂��B����͂���10��ނ̏������ȒP�ɂ��͂Ȃ����܂��傤�B
�����q����
�@�@���Ѝ�a�����̗��q�A�ݕt�M������Ѝ��M�̎��v�̕��z�Ȃǂ��琶���鏊��
���z������
�@�@�����̔z���A��]���̕��z�A�،������M���i���Ѝ��M�ȊO�j�̎��v���z�Ȃǂ��琶���鏊��
���s���Y����
�@�@�s���Y�A�y�n�̏�ɑ����錠���A�D���A�q��@�̑ݕt���Ȃǂ��琶���鏊��
�����Ə���
�@�@�����ƁA�����ƁA�����ƁA�T�[�r�X�ƁA�_�ƁA���ƁA���̑��̎��ƂŁA
�@�@�p���I�ɑΉ��čs�����Ƃ��琶���鏊��
�����^����
�@�@�����E�ܗ^�Ȃǂ̏����i��Ђ��疳���q�ŋ��K�������̌o�ϓI���v��
�@�@�����x���̋��^�����܂݂܂��j
���ސE����
�@�@�ސE�蓖���A�ސE�ɂ���Ĉꎞ�Ɏ��A���^�̐�����������
�@�@(��ƔN����N���ł͂Ȃ��ꎞ���Ŏ�����ꍇ���܂܂�܂�)
���R�я���
�@�@5�N���ď��L���Ă����R�т̂��Ĕ�������A���͗��̂܂ܔ���������
�@�@(���L���Ԃ�5�N�ȉ��̏ꍇ�͎��Ə����܂��͎G����)
�����n����
�@�@�y�n�E�������̏��n�A�����̏��n�A���Ɨp�̌Œ莑�Y��ƒ�p�̎��Y����
�@�@���n�ɂ���Đ���������
���ꎞ����
�@�@�N�C�Y�̏܋��▞���ی����ȂǁA�c����ړI�Ƃ��Ȃ��ꎞ�I�ɐ���������
���G����
�@�@�N���≶���Ȃǂ̌��I�N�����A��c�Ɨp���̗��q�A���e�����ŁA�u�����Ȃǂ̂悤�ɁA
�@�@����9��ނ̏����̂ǂ�ɂ������Ȃ�����
�@�������Ĉ�x�ɂ��͂Ȃ�����ƁA��ނ����������ĔY��ł��܂��܂���ˁB
�ł��A���ꂼ��̏����ɂ���ď����̌v�Z���@��m��\���̗L�����Ⴂ�܂��̂ŁA
�����ł��v�Z����ɂ́A�܂��A�������ǂ̏����ɋ敪�����̂��f����K�v������܂��B
�m��\���̍ۂɂ́A�����ӂ��B
��R�W�b�@�l���Ɛł̊�

�@�����ł�Z���ł̊m��\���ɂ��Ă͂悭���ɂ��܂����A�l�̎��Ɛłɂ��Ă͂��܂育���m�łȂ����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����ō���́A�ӊO�ƒm��Ȃ��l���Ɛłɂ��Ă̂��͂Ȃ��ł��B
�@�l���Ɛł́A�l���s�����̎��Ƃɑ��āA���̎��Ƃ̎��������͎��Ə��̏��݂���s���{������ۂ���܂��B�ΏۂƂȂ�Ǝ�Ɛŗ��͉��L�̂Ƃ���ł��B
���@����Ǝ�i�R�V�Ǝ�j�@�ŗ��F�T��
�@�@�@���i�̔��ƁA�s���Y�ݕt�ƁA�����ƁA���ԏ�ƁA�����ƁA���H�X�ƁA
�@�@�@���̑���ʂ̉c��
���@����Ǝ�i�R�Ǝ�j�@�ŗ��F�S��
�@�@�@�{�Y�ƁA���Y�ƁA�d�Y������
�@
���@��O��Ǝ�i�R�O�Ǝ�j
�@�@�E�ŗ��F�T��
�@�@�@��ƁA�ٌ�m�ƁA�ŗ��m�ƁA�R���T���^���g�ƁA ���e�ƁA
�@�@�@���e�ƁA���̑��̎��R��
�@�@�E�ŗ��F�R��
�@�@�@����܁E�͂�E���イ���̎���
�@�@
�@�Ŋz�̌v�Z�͑O�N�̂P���P������P�Q���R�P���܂ł̂P�N�Ԃ̎��Ƃ��琶����
�������z����ɂ��Čv�Z����܂��B
�@���@�Ŋz�̌v�Z���@
�@�@�@�@���Ƃ��琶���鏊���{�F�\�����ʍT��
�@�@�@�@�@�@�@�|�e��T���|���Ǝ�T���i�N�Q�X�O���~�j���ېŏ������z�~�ŗ�
�u���Ƃ��琶���鏊���v�Ƃ́A�������z����K�v�o����������������̂ŁA���̌v�Z��
�T�������ł̌v�Z�Ɠ������@�ōs���܂��B �������A�����ł̐F�\�����ʍT���̓K�p��
����܂���̂ŁA�������z�ɉ��Z����邱�Ƃɒ��ӂ��Ă��������B
�@�܂��A�\���ɂ��Ă͏����ł̊m��\������Ŗ����ɒ�o�����ꍇ�͕s�v�ƂȂ�A
�s���{�����瑗�t�����[�Œʒm���ɂ���ĂW���ƂP�P���ɔ[�߂邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�[�߂����Ɛł̋��z�͏����łɂ����鎖�Ə����E�s���Y�����E�R�я����E�G������
�K�v�o��Ƃ��ĎQ���ł��܂��̂ŁA�m��\���̍ۂɂ͖Y��Ȃ��悤�Ɍv�サ�Ă��������ˁB
��R�X�b�@�ΘJ�w���T���̊�

�@�ΘJ�w���T���Ƃ́A�[�ŎҖ{�l�������Ȃ���w��ł���w���ŁA���̏��������ȉ��̏ꍇ�ɁA�����̍T�����邱�Ƃ��ł���
���x�ł��B
�@�ΘJ�w���Ƃ́A���̔N��12��31���̌����ŁA���̎O�̏����̂��ׂĂɓ��Ă͂܂�l�ł��B
(1)�@���^�����Ȃǂ̋ΘJ�ɂ�鏊�������邱��
(2)�@���v�������z��65���~�ȉ��ŁA������(1)�̋ΘJ�Ɋ�Â�
�@�@ �����ȊO�̏�����10���~�ȉ��ł��邱��
�@�Ⴆ�A���^���������̐l�̏ꍇ�́A���^�̎������z��130���~�ȉ��ł�����^�����T��65���~�����������Ə������z��65���~�ȉ��ƂȂ�܂��B
(3)�@����̊w�Z�̊w���A���k�ł��邱��
�@���̏ꍇ�̓���̊w�Z�Ƃ́A���̂����ꂩ�̊w�Z�ł��B
�C�@�w�Z����@�ɋK�肷�鏬�w�Z�A���w�Z�A�����w�Z�A��w�A
�@�@�������w�Z�Ȃ�
���@���A�n�������c�́A�w�Z�@�l���ɂ��ݒu���ꂽ��C�w�Z����
�@�@�e��w�Z�̂��������ے��𗚏C���������
�n�@�E�Ɣ\�͊J�����i�@�̋K��ɂ��F��E�ƌP�����s���E�ƌP��
�@�@�@�l�ň��̉ے������C���������
�@�ȏ�̂����ꂩ�̊w�Z�ɓ��Ă͂܂邩�ǂ���������Ȃ��Ƃ��́A
�ʊw���Ă���w�Z�������Ŋm�F���Ă��������B
�@�ߔN�A��w�ʐM����̔��B�ɂ��A�ʐM���̊w�Z�ɍݐЂ���ΘJ�w���������Ƃ����Ă��܂��B�ߐł��Č���Љ�ɍ��������C�t�X�^�C�����l���Ă��������ł��ˁB
��S�O�b�@����ł̊�

�@�m���Ă���悤�Œm��Ȃ�����ł̂��b�ł��B
������ł̂�����
�@����̕��i��T�[�r�X�ɉېł���ʊԐڐłƂ͈قȂ�A����ɍL�������ɕ��S�����߂�Ԑڐłł��B����̂��̂��ېőΏۂƂ���u���ڏ���Łv�ƍŏI�I�ȏ���̑O�i�K�ʼnۂ����u�Ԑڏ���Łv�ɕ��ނł��A�O�҂ɂ̓S���t�ꗘ�p�łȂǂ��Y�����A��҂ɂ͎�łȂǂ��Y�����܂��B
�@�Ԑڏ���ł͂���ɉېőΏۂƂ��镨�i�E�T�[�r�X�̏�������̂��̂Ɍ��肷�邩�ǂ����ɉ����u�ʏ���Łv�Ɓu��ʏ���Łv�ɕ��ނ���܂��B
�@���̏���ł́A���Y�y�ї��ʂ̂��ꂼ��̒i�K�ŁA���i��i�Ȃǂ��̔������s�x���̔̔����i�ɏ�悹����Ă�����܂����A�ŏI�I�ɐłS����̂͏���҂ƂȂ�܂��B
���ŗ�
�@����25�N5�����݂̐ŗ��́A4���ł��B�܂��A����ł̂ق��ɒn������ł��ʓr����Ŋz��25��(����ŗ��Ɋ��Z����1������)�ېł���邱�Ƃ���A���������킹���ŗ���5���ƂȂ�܂��B
���[�ŋ`����
�@��������̔[�ŋ`���҂́u�l���Ǝҁv�Ɓu�@�l�v�ł��B
�@��������̏ꍇ�ɂ́A���Ǝ҂́A��ېŎ���������A���ƂƂ��čs�������Y�̏��n��ݕt���A�̒ɂ��ď���ł̔[�ŋ`�������ƂɂȂ��Ă��܂��B
�@���̂悤�ɁA��������̏���ł̔[�ŋ`���҂͎��Ǝ҂ł�����A���Ǝ҂łȂ��҂͔[�ł̋`���͂���܂���B
�@�Ȃ��A���Ǝ҂Ƃ͌l���Ǝҁi���Ƃ��s���l�j�y�і@�l�������A�@�l�ɂ͊�����Г��̉c���@�l�A�����@�l�A���v�@�l���̂ق��l�i�̂Ȃ��Вc�����@�l�Ƃ݂Ȃ���Ă��܂��̂Ō����@�l�A���v�@�l����l�i�̂Ȃ��Вc�����ېŎ��Y�̏��n�����s���ꍇ�ɂ͔[�ŋ`���҂ƂȂ�܂��B
�@�܂��A����n�������c�̂����Ǝ҂ƂȂ�ېŎ��Y�̏��n�����s������[�ŋ`���҂ƂȂ�܂��B
�u����Łv�Ƃ������t���Ȃ����͖������炢�@����Ŏg���Ă��܂��B�g�߂Ȑł̈�Ƃ��Ċo���Ă��������ł��ˁB